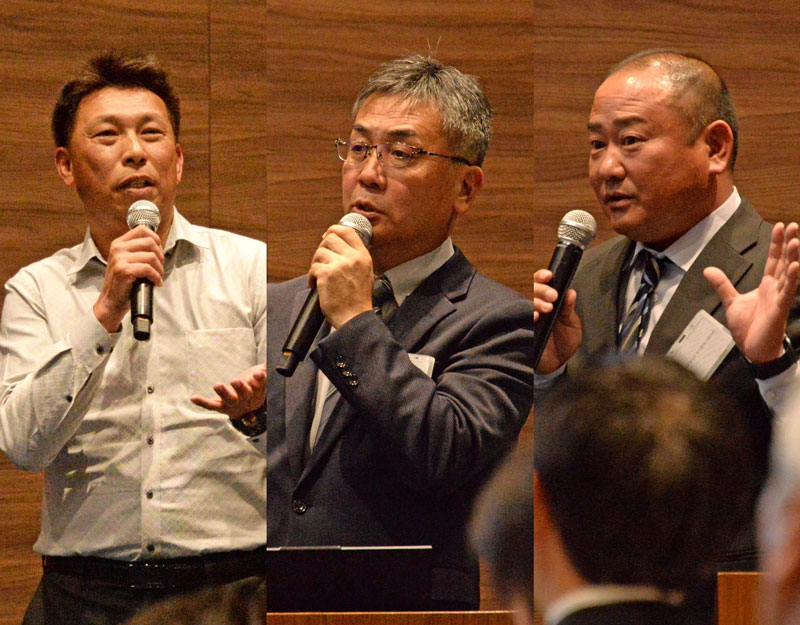- HOME
- ニュース
- その他競技部門

ニュース その他競技部門
令和6年度 全国指導者中央研修会
「部活動の地域移行」と「体罰・暴言問題の根絶」にフォーカス。
ソフトボール指導者の今後の ″あり方・役割・展望″ を考える!
全国の指導者の代表41名が参加。
指導者の今後について考え、議論
「部活動の地域移行」に関わる新たな取り組みを発表。
※左から、井ノ口敏功 氏、關根邦明 氏、髙橋秀幸 氏
「ソフトボールの未来のために、できること」
それぞれが「新たな一歩」を踏み出している
地区別研修会では活発に意見交換!
「体罰防止に向けた取り組み」をテーマに、
日本体育大学教授・南部さおり 氏が講演
指導者資格の周知・指導者制度の発展を!!
令和6年度全国指導者中央研修会が、去る2月8日(土)・9日(日)の両日、東京・Japan Sport Olympic Squareにおいて開催された。
研修会には、(公財)日本ソフトボール協会指導者委員会をはじめ、全国各都道府県支部協会の指導者委員長ら計41名が参加。ソフトボールの普及・振興を図る上で極めて重要な役割を担っている全国の指導者の代表が、ソフトボール指導者として「今後どうあるべきか」を考えるとともに、より「主体性」を持った指導者養成の体制づくりを推進させていくべく、活発な意見交換を行った。
また、大きく変動する社会の中でソフトボール指導者の現場での課題を洗い出し、社会から「真に求められる指導者」を養成していくため、今後どのようなことに取り組んでいかなければならないのかを議論。全国から集まった代表者たちがそれぞれ考えを持ち寄り、さまざまな分野について熱く語り合う場となった。
◎研修会初日/2月8日(土)
研修会初日、冒頭では(公財)日本ソフトボール協会・瀬戸山章 事業総括本部長、岩﨑眞美 指導者委員会担当理事、栗山利宏 指導者委員長が挨拶に立ち、現在の日本協会の取り組みや直近の課題、今回の中央研修会の趣旨・流れを説明。指導者委員会の方針を踏まえ、参加者全員へ活発な意見交換を求めた。
この後、昨今推進される ″部活動の地域移行″ (※これまで中学校・高校の教員が担ってきた部活の指導を地域のクラブ・団体等に移行すること。具体的には、スポーツ庁と文化庁が2022年12月に策定したガイドラインに基づき、まずは2023年度から3年間かけ『公立中学校』の『休日』の『運動部』の部活動を優先して、段階的に地域移行しようとしている)を受けて、富山県・關根邦明 氏、愛知県・井ノ口敏功 氏、大分県・髙橋秀幸 氏の3名が「部活動の地域移行に関わる新たなクラブ運営やアカデミー等の運営(運営の工夫、指導者の養成・育成・役割)について」事例発表。
富山県・富山いずみ高校教諭の關根邦明 氏は「学校の部活動だけに頼らない、新たな取り組み」として、自身が勤務する富山いずみ高を会場に毎週水曜夜間「富山ソフトボールアカデミー」と銘打ったソフトボール教室を開催していることを紹介。
「県内のソフトボール競技人口(特に小中高生)が年々減少している」状況を何とか打開しようと、まず「競技の楽しさ」を伝えることを目的に、小学1年生から中学3年生までを対象とした ″練習だけ″ のソフトボール教室(ソフトボール体験会)を企画・実践。当初5人だった受講生が、富山市内の学校等での根気強いPRの成果もあって11人まで増えた「嬉しい現状」があることをまず報告すると、より発展させていくためのポイントとして「場所・指導者・資金」の3つを挙げ、「学校・行政とこれまで以上に連携を深め、練習環境や設備を充実させていくこと。指導者資格を有し、一貫指導が行えるソフトボール指導者を継続的に養成・育成していくこと。ポスターやチラシ、SNS等を柔軟に活用して粘り強くPR活動を行い、周囲の理解・信頼を得ながら、さまざまな支援獲得(地区の補助金や企業からのバックアップ等)へつなげる『地道な取り組み』『働きかけ』を続けていくことが重要になる」と今後の展望を述べた。
愛知県・愛知PHOENIX(※中学男子クラブチーム)監督の井ノ口敏功 氏は ″学校の教員とは違う″ 自らの指導環境を踏まえ、「地域クラブチーム」結成の経緯、実際にクラブチームを運営し、活動する中での苦労や選手たちの成長の足跡を紹介。
自らも日本のトップリーグでプレーした経験を持つ井ノ口氏(※井ノ口氏は日本男子リーグに所属する豊田自動織機で13年プレー。チームのコーチも務め、現役引退後は『地域指導者』として中学男子硬式野球や高校女子ソフトボールの指導をサポートしてきた)は、息子が高校でソフトボールをはじめたことがキッカケとなり ″ソフトボールの指導意欲″ が再び高まり、2020年地元・愛知で「中学男子クラブチーム」愛知PHOENIXを結成。第1回目の体験会には45人の参加があったものの、入団は僅か3名。さらに入団式の翌日からコロナ禍で活動自粛を余儀なくされ……初代(第1期)メンバーが最終的に一人となってしまった当時の「リアルなエピソード」も盛り込みながら、クラブチームを運営していくための要点を解説。規約(役員:代表、マネージャー、父母代表等の選出、運営費、指導方針について)の作成にはじまり、役員会・総会を定期的に開催すること、特に「指導者の役割や指導の仕方」をコーチングスタッフで「共有する」ことは非常に大切であり、自らと同じ元・実業団ソフトボールチームのプレーヤーで構成された愛知PHOENIXの指導者にも「役割として、選手たち:投手、捕手、内野手、外野手の『良き相談役』となること。指導の仕方も、教える側の一方的な指導ではなく、教えられる側の思い・考え・意見も聞き入れ、『尊重』すること。監督・コーチが日々の問題点を常に『共有』し、『修正』していくこと」を徹底していると強調した。
(公財)日本ソフトボール協会指導者委員会副委員長で、大分県・大分ドリームガールズ(※中学女子クラブチーム)総監督も務める髙橋秀幸 氏は、現在、大分県ソフトボール協会が ″ソフトボールの未来″ を見据え「総力を挙げて」取り組んでいる「大分ソフトボールドリームプロジェクト」を紹介。
事業内容は ①ジュニア層の育成 ②普及をテーマにしたソフトボール未体験者へのアプローチ ③小中学生のサポート(指導支援) ④ジャンプアップアカデミー(中学3年生をサポート:高校入学までの練習環境を提供) ⑤県中学生選抜チームのサポート・強化(都道府県対抗中学生大会に向けたサポート・強化)と5つあり、自らが総監督を務める「大分ドリームガールズ」はまさにこのプロジェクトによって設立された「中学女子クラブチーム」である(※大分ドリームガールズソフトボールクラブは、子どもたちを取り巻くスポーツ環境の変化に対応するため『学校部活動と共存すること』を前提に、将来的に持続可能な中学生クラブチームの創部をサポートする(一社)大分県ソフトボール協会『大分ソフトボールドリームプロジェクト』によって、2019年に設立されたソフトボールチームである)ことを説明。また、プロジェクトの立ち上げ・チーム創部のキッカケが富山県同様「県内のソフトボール競技人口(特に小中高生)が減少し続けている」厳しい現実に直面し、「このままではソフトボールをする子どもたちがいなくなってしまう……」という強い危機感にあったこと。「今後は ″部活動の地域移行″ が推進されていく時代傾向をできるだけ『前向き』にとらえ、私たちはむしろ ″その風向きを追い風に変えていく″ ぐらいの気概で、ソフトボールの未来を創造する『具体的なアクション』を起こす必要があるのではないか!」と参加者へ熱く投げかけた。
研修会初日の最後は、全国各ブロック(北海道・東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)に分かれての地区別研修会/グループディスカッションを実施。「指導者養成事業や育成事業における課題の共有と改善策」をテーマに、活発な意見交換が行われた。
◎研修会2日目/2月9日(日)
研修会2日目は、日本体育大学・スポーツ文化学部武道教育学科教授の南部さおり氏が「体罰防止に向けた取り組み」をテーマに講演。
児童虐待やスポーツにおける体罰・ハラスメントの問題を研究する南部氏は、冒頭で「現在、ジュニアスポーツで暴言や体罰を受けている子どもは何パーセントいると思いますか?」と参加者へ問いかけ、自身の調査・分析結果をもとに現代スポーツにおける「試合中の暴言・暴力」「練習中の暴言・暴力」の実態を紹介。2022年に兵庫県姫路市・姫路女学院高校女子ソフトボール部で起きた「男性顧問の体罰」(指導していた生徒への暴力行為)にも触れ、「このような痛ましい事実を真摯に受け止め、再発防止に努めることはもちろん、すべての指導者が今一度『体罰・暴言問題』と向き合わなければならない」と投げかけると、ジュニア期の指導者の影響力について「スポーツ好きな児童は、スポーツ指導者に『理想の大人像』『めざす人物』を投影しやすい。そこで求められるのは技術よりも指導者の『人間性』であり、いかに情緒的に触れ合うか、どのような言葉がけをするのか、児童の人生観に大きな影響を及ぼすことを強く自覚する必要がある」。 ″厳しさ″ と ″叱る″ の違いについては「厳しさの本来的な意味とは、『妥協をしない』ことや『要求水準が高い』ことであり、そこにネガティブな感情を与える必要はない。苦しみが成長につながるのは、それが他から与えられたときではなく、自ら主体的・自律的に苦しみを乗り越えるとき。そのために周囲がすべきことは、本人が『やりたい』と感じる目標を見つけるサポートをすること。目標に向かう『冒険』を成功させるための武器を与え、道筋を示すことであって、叱ることはむしろそれを阻害する行為である」と述べ、日本のスポーツ界に根強く残る「理不尽に耐える」というキーワードについても「そもそも他人から与えられる『本来不必要な我慢』『理不尽な苦痛』では、人は強くならない。人の学びを促進し、成長を促す効果が高いのは『自分の意志』で決断し、やりたいことのためにしていると感じられる我慢である」と解説。「指導者の意識改革」の必要性を改めて語った。
この後、講演のテーマ・内容に沿って再び地区別研修会/グループディスカッションを実施。「体罰防止に向けた取り組み」について討議が行われ、討議後は各グループの代表者がそれぞれ意見を発表。議論・発表の中で参加者が連帯感を深めるとともに、各々の現場の実情、指導における経験談を積極的に伝え合いながら、自分たちが中心になってこの問題を根絶していこうとする「熱意ある姿勢」が感じ取れる研修となった。
時代は流れ、指導者を取り巻く環境は日々変化している。「指導者の役割」「指導者に求められるもの」も当然変わってきており、その時代・社会の変動に ″どう向き合い、どのように対応していくか″ が引き続きカギとなるだろう。
一方で、ソフトボールにおいては「指導者資格の周知」「指導者制度の発展」という部分にもメスを入れていかなければならない。実際現場では ″資格はあくまで大会に出るためのもの″ ″資格を取得していても、更新には至っていない″ といった声を少なからず聞く。指導者資格、資格取得の「本質とは何か」を今一度考え、「あるべき姿」を追求していくこと、そしてそれを「具現化」する手段・方策を見出していかなければならない時期にきていると言えるのではないだろうか。